産業廃棄物をアップデートする男
ビジネスの本質は、金を稼ぐことでも、競争に勝つことでもない。仕事を通じて自分を表現し、他者とつながり、社会に何かを還元できるかどうか。そんなシンプルな問いに対する答えを、真っ向から探し続けている男がいる。 神奈川県川崎市。工業地帯の喧騒と、人々の絶え間ない営みが交錯するこの街には、鉄とコンクリートの塊が生み出す無機質な風景と、人々の汗が染み込んだ現場のリアルが共存している。街を歩けば、砂を巻き上げながら行き交う大型トラック、積み上げられた無骨なコンテナ、工場から立ち上る蒸気、そして何よりも、そこに生きる人々の息遣いを確かに感じることができる。 そんな川崎の片隅で、産業廃棄物の概念を根底から覆そうとしている男がいる。光田興熙、株式会社光洲産業の代表取締役だ。父の背中を見て育ち、一度は異なる業界を経験した後、家業を継ぐ決意をした男である。

果たしてそれは“ゴミ”なのか?

光田は最初から経営者だったわけではない。大学を卒業後、大手商社に就職し、世界の物流や市場経済の仕組みを学んだ。しかし時が経つにつれ、彼の中には「もっと直接的に社会に貢献できる仕事がしたい」という思いが膨らんでいく。父の経営する光洲産業に戻る決意をしたのは、その思いが限界に達したときだった。 2016年、29歳で光洲産業に入社した光田は、当初は会社のすべてを学ぶことに徹した。350人の社員、100台のトラック、5つの工場。圧倒的な規模に圧倒されながらも、彼は現場を回り、実際に手を動かしながら経営の本質を探ろうとした。違和感があった。「廃棄物が工場に入って、廃棄物として出ていく。これって、一体何のための仕事なんだ?」彼は自問した。もちろん、産業廃棄物処理業は社会に必要な仕事だ。しかし、それだけで満足していいのか?「ゴミを処理する」のではなく、「ゴミに新たな価値を与える」仕事にしたい…その思いが彼を突き動かした。 光田は、従来の廃棄物処理業の在り方に疑問を持ち、新たなビジネスモデルを構築することを決意した。その第一歩が、「ゴミを価値あるものに変える」試みだった。リサイクル材をただ燃料として供給するのではなく、新たな製品として市場に送り出すことを考えたのだ。試行錯誤の末、彼はプラスチック廃棄物を再資源化し、建築資材として輸出するプロジェクトを立ち上げた。2023年、台湾企業との提携が決まり、日本の廃プラスチックを原材料として再活用するスキームを確立した。これは単なるリサイクルではなく、「ゴミを価値ある商品にする」という彼の哲学を体現したプロジェクトだった。 また、彼は石膏ボードの廃棄物を粉砕し、新たな建築資材として生まれ変わらせる事業にも挑戦した。廃棄物処理業者が建材を作る…この異端とも言える挑戦は、業界内でも驚きをもって受け止められたが、光田は一切気にしなかった。「誰かがやらなきゃいけない。でもみんなやらないなら、自分がやるだけなんです。」
リサイクルが好きです
光洲産業のクレドは「リサイクルが好きです。」このシンプルなフレーズは、単なるキャッチコピーではなく、企業の哲学そのものを表している。「好き」という感情は強制できるものではない。しかし、リサイクルを義務や単なる業務としてではなく、創造の場として捉えたとき、それは新たな価値を生み出す力となる。光田は「廃棄物は終わりではなく、始まり」と考え、社員一人ひとりが誇りを持ち、楽しみながら働ける環境をつくることに注力している。 クレドには、リサイクルという行為を通じて社会を変え、未来を創造するという決意が込められている。それは、ゴミを単なる不要物と見るのではなく、新たな可能性の種と捉える思想でもある。光田は社員に対して「リサイクルを楽しめる職場こそが、真の社会貢献につながる」と繰り返し伝え、実際の事業改革を進めている。 光洲産業が目指すのは、リサイクルを義務ではなく、企業と社員が共に成長する場として捉えることだ。このクレドが根付いたとき、産業廃棄物処理業界はもはや「処理業」ではなく、「価値創造業」へと進化するだろう。
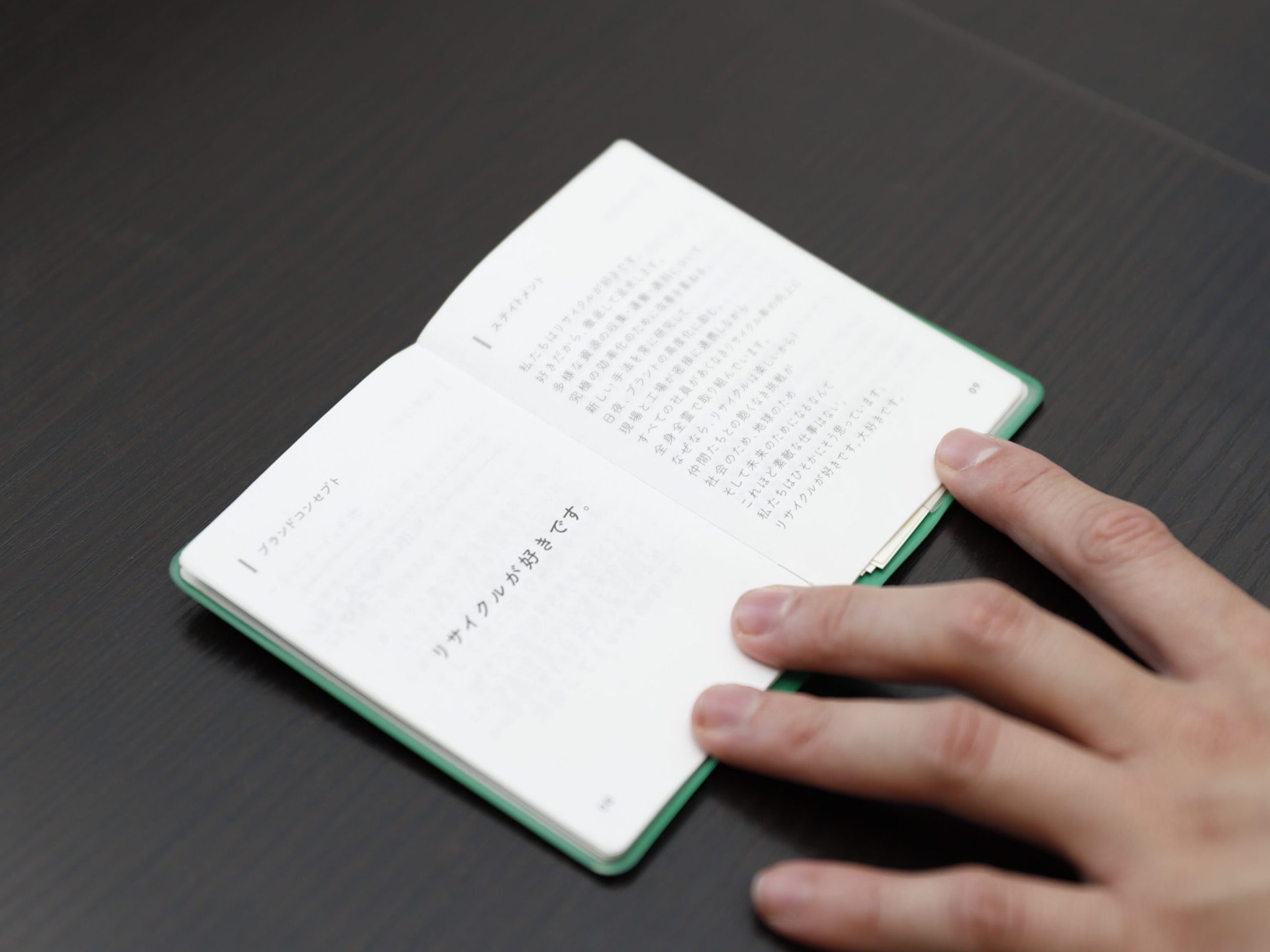
誰もが避けたがる仕事にこそ価値がある
内村鑑三は「二つのJ(Jesus and Japan)」を掲げ、信仰と愛国心の両立を追求し、信念を貫きながらも日本のために尽くした。彼は国家や制度に盲従することなく、真の道義とは何かを問い続け、自らの思想を実践した。無教会主義を提唱し、既存の宗教組織に属することなく信仰を深め、独立した精神のもとで倫理と社会貢献の重要性を説いた。その生き方は、既成概念に縛られずに自らの信念を貫く者にとって、一つの指針となり続けている。 光田もまた、「リサイクルは楽しい」と言い切る。それは単なるスローガンではなく、仕事を通じて社会を変え、社員を幸せにすることが自分の使命だという、果てしなく強い信念の表れだ。内村が既存の価値観に縛られず、自分の道を突き進んだように、光田もまた、業界の常識を打ち破る道を歩んでいる。 産業廃棄物処理業は、一般的に「汚い仕事」と思われがちだ。しかし、彼は違う。「誰もがやりたがらない仕事に、新しい価値を見出せるかどうか。それが人生を面白くするんです。」仕事は、ただの生計の手段ではない。自分が何かを生み出し、社会に貢献できるものにすることができるかどうかが、大事なのだ。 光田のような人間が増えれば、この国の産業はどんなものでももっと面白くなるはずだ。彼の挑戦は、廃棄物処理という枠を超え、働くことそのものの意味を再定義しようとしている。僕らは「仕方なく働く」のではなく、「働くことを楽しむ」ことができるのか? その問いを、彼の生き様から学ぶべきかもしれない。



