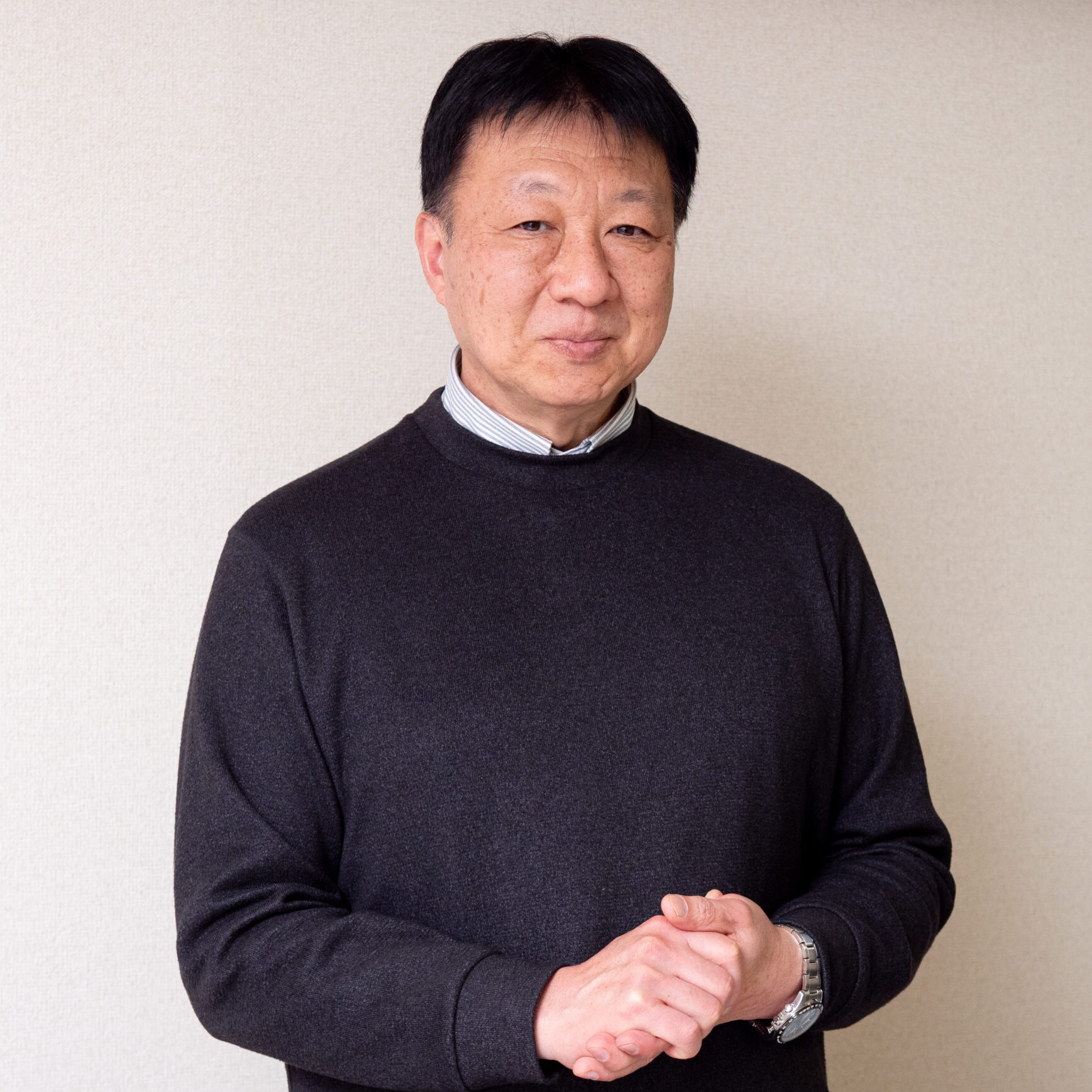総合力が求められる専門職
マンション管理という分野は、日本が高度成長期を駆け抜けた後に独特の進化を遂げてきた。戦後の住宅不足を解消するために建てられた集合住宅がやがて経年劣化し、人々の暮らし方も多様化する中で、「どうやってこの建物とコミュニティを維持していくのか」という新たな課題が表面化したのだ。数十世帯、時には数百世帯もの人々が同じ建物に暮らす。その上、建物や設備に関わる修繕、敷地や共用部を巡るルール決め、住民間の意見対立など、問題は多岐にわたる。そんな複雑な状況を一手に支える「マンション管理士」という国家資格が存在することを、どれだけの人が知っているだろうか。 マンション管理士の仕事は、単なる不動産の知識や建物の管理だけにとどまらない。法務・財務・建築、そして時に人間関係の調整という“総合力”が求められる専門職だ。建物を守るだけでなく、そこに暮らす人々を支え、コミュニティ全体が円滑にまわるよう後押しする。ここには、大きな可能性が眠っている。古くからの住民もいれば、新しく引っ越してきた住民もいる。意見が合わない人同士が同じ階段や廊下を使い、時にはトラブルも生まれる。でも、その一つひとつを丁寧に拾い上げ、自治を促進させる。それこそが「マンション管理士」の役割だ。 そんなプロフェッショナルの一人が、合同会社あかりメイトを率いる峰平宣明代表である。大阪出身、神奈川に移り住んでからはすでに30年。現在は「峰平マンション管理士事務所」としても活動し、数多くの管理組合をサポートしている。その歩みには、マンション管理士という仕事の可能性を照らす、強い意志と地道な実務経験が詰まっている。

その判断が住民の生活に直結する
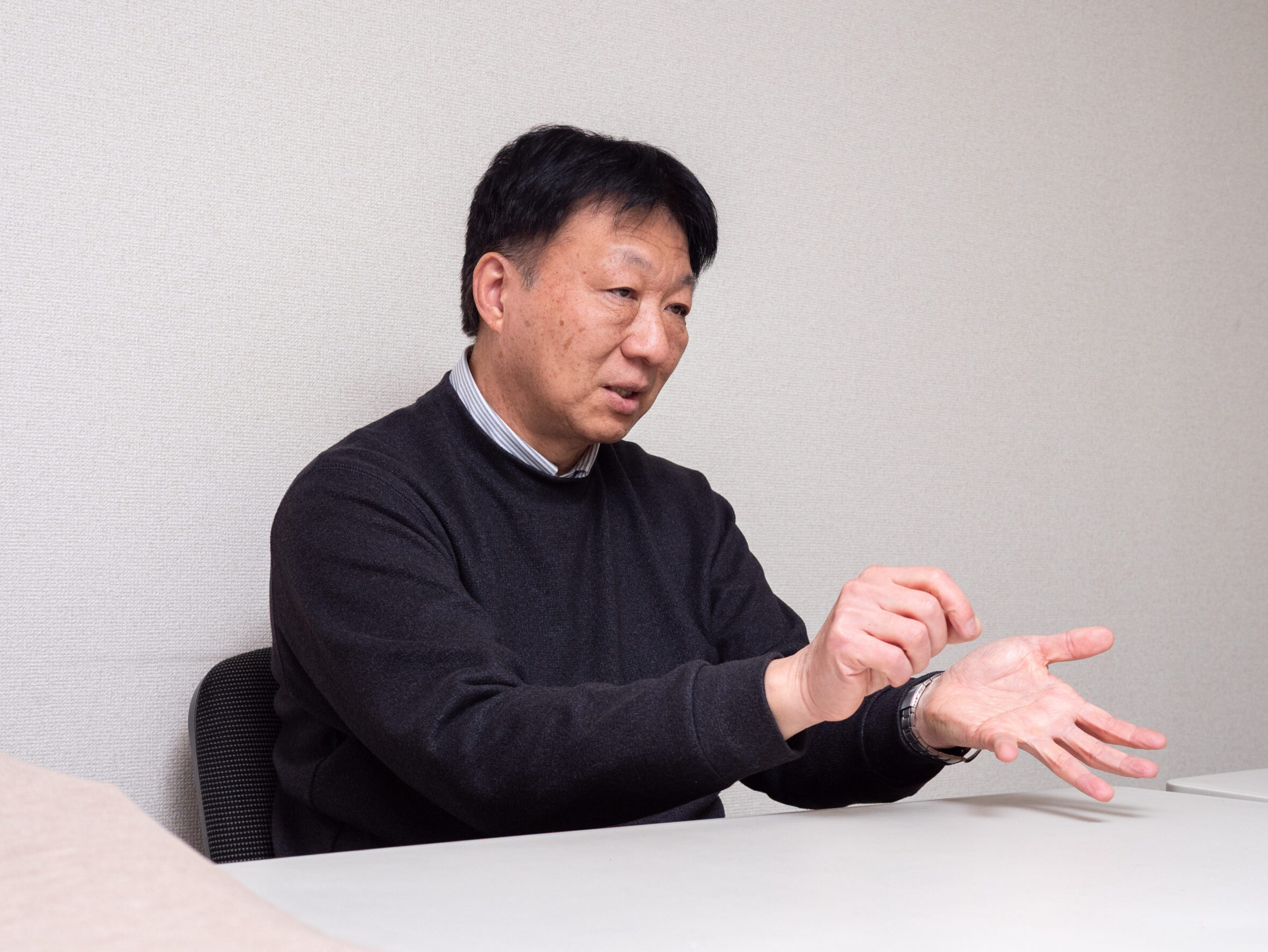
不動産会社に勤務していた頃、そしてゼネコンの現場監督をしていた頃から、峰平は建物に関わる実務にじっくり向き合ってきた。大手マンション管理会社にてフロントマン、つまり管理組合の担当者として数多くの物件を任された経験は、その後のキャリアを決定づける。フロントマンは管理組合の理事会や総会に出席し、住民と管理会社の橋渡しを行う最前線のポジションだ。マンションには様々な住民が暮らしているため、意見が衝突する場面も少なくない。修繕積立金をどうするか、騒音問題やペット飼育ルールをどう取り扱うか…一つひとつのテーマが住民の生活や財産に直結する。だからこそ、単なる事務作業以上に、粘り強い説得や合意形成が求められるのだ。 「最初はただひたすら大変でしたよ」と彼は笑う。管理組合の担当者になったばかりの頃は、「管理会社がやれと押しつけてきた」と住民から誤解される場面もあったし、そこに至るまでの経緯をしっかり説明していないと「いつの間にこんな工事に決まっていたの?」と不満をぶつけられることもあったという。しかし、ひとつの物件を何年にもわたって担当するうちに、住民の顔と名前、性格、そしてそれぞれの思いが少しずつ見えてくる。「誰がどんなことにこだわっていて、何を大事にしているのか」という点をつかむことで、交渉や提案はスムーズになっていく。 それはまさに現場主義の徹底だった。書類のやりとりだけではわからない微妙なニュアンスを、実際に足を運んで住民と話すことで察知する。時には雑談まじりに、エントランスの植栽の状態を一緒に眺めるだけで「今こういうところで困っているんだよね」と住民が本音をこぼすこともある。そのひとつひとつが、後の大きな問題の芽をつむ鍵になり、あるいは管理組合としての理想像を描くヒントになったりする。「結局、人と人とのコミュニケーションなんです。」という言葉には、峰平がフロントマンとして培った経験が凝縮されている。 やがて彼は、大手管理会社での仕事に一区切りをつけ、マンション管理士として独立。合同会社あかりメイトを立ち上げ、さらにマンション管理士事務所として本格的に活動を開始した。思い返せば、業界自体が法制度の変化や建物の老朽化問題に翻弄される中で、多くの管理組合がサポートを必要としていた。けれども、本当に現場の声を細かく拾い上げ、丁寧に伴走してくれる専門家は意外に少ないのが実情だったのだ。「管理組合の方々がご自身でネットを検索して情報収集しても、そこには抽象的な法律の話や理想論ばかりが並んでいて、何から手をつければいいかわからない」というケースは多いという。
住民を動かす技術
実際、峰平がこれまで対応してきた管理組合は、延べ150件にも及ぶ。そこには築年数が浅い物件もあれば、既に何十年も経って共用設備が綻びはじめた物件もある。住民の年代構成や財政状況もまるで違う。その一つひとつに対し、法律や規約のチェックだけでなく「こんな段階的な進め方なら、無理なく合意形成できますよ」といった具体案を提示していく。時には会合の場で住民に囲まれ、「そんなに費用を出せるわけないだろ」と声を荒げられることもあったそうだ。それでも一歩も退かず「では、今すぐ大きな工事は難しいとしても、まずはここだけ押さえておきましょう」と優先順位を解きほぐしていく。その粘り強さが功を奏し、トラブルが解決した後に「ありがとう」と感謝される瞬間があるからこそ、この仕事はやりがいが尽きないのだと、峰平は言う。 一見地味に映るかもしれないマンション管理。しかし、その向こうには多種多様な人間模様があり、何十戸もの家族の暮らしがある。中には高齢化が進んでいて、理事会を担う人が少なくなっている物件もあるし、外国籍の住民が増えてコミュニケーションに苦労するケースもある。管理組合が力を発揮できず、管理会社任せになってしまえば、必要な修繕を先送りし、結果的に大幅なコストがかかってしまうこともある。だからこそ、マンション管理士の腕の見せ所は多い。建物や法制度の知識に加え、住民を巻き込み、「自分たちの住まいを自分たちで守っていこう」というモチベーションを引き出す力が求められるのだ。 いわゆる「派手な改革」ではなく、丁寧な対話と合意形成。それこそが峰平のスタイルの根幹だ。様々な価値観をもった住民たちが暮らす集合住宅の場では、「一方的に指示を押しつける」だけでは機能しない。むしろ住民の中からリーダー的存在を見つけて、彼らが主体となって動けるように下支えする。その姿勢こそがコミュニティを豊かに育てる鍵となる。

リーダーシップとは分け合い引き出すこと
ここで、アメリカの女性社会活動家ミルドレッド・C・フリックを紹介したい。彼女が掲げた名言の一つに、「本物のリーダーシップとは、分け合い、引き出すこと」という言葉がある。リーダーが一方的に命令するのではなく、チームのメンバーそれぞれが持っている力を見極めて、それを引き出しながら共通のゴールへ向かう。そのためには、お互いの意見を尊重し、合意をつくり、納得して行動してもらう必要があるのだ。マンション管理でもまさに同じで、管理組合の理事長や理事会メンバーだけに負担を押しつけるのではなく、全住民がそれぞれの立場で関心を持って協力することが望まれる。ミルドレッド・C・フリックの考え方は、「住民同士が主体的に動くコミュニティづくり」という点で、峰平の仕事とも深く共鳴する。 このような理念を口にするのは簡単だが、実際は根気がいる。説明しても理解を得られない住民がいるかもしれないし、長年の不信感から対立が根深くなっている物件もあるかもしれない。でも、そこを諦めず、一つひとつ課題をクリアするたびにコミュニティが少しずつ前進していくのを、峰平は何度も見てきた。「あんなにギスギスしていた理事会が、気づけば和やかに話し合っているんですよ」と、嬉しそうに語る。これは表向き派手なプロジェクトではないかもしれないが、そこには人々の暮らしを守り、生活を安全・快適にする“確かな手応え”がある。 最後に、若い世代へのメッセージを尋ねると、峰平は少し照れながら、しかし真剣な眼差しで答えてくれた。「マンション管理士って、まだまだ知名度が低いんですね。でも、人々の生活と財産を支える、すごくやりがいのある仕事です。僕が言いたいのは、“自分から現場に足を運んでみよう”という姿勢が大事だということ。ネットの情報やデスクワークだけじゃわからない、リアルな悩みや想いが、そこにはあるんです。」この言葉は、決してマンション管理に限らず、さまざまな仕事や生き方にも当てはまるはずだ。教科書やSNSで流れてくる情報だけを鵜呑みにするのではなく、実際に現地に行って、人と話して、肌で感じる。その先にこそ、本当に必要な解決策が見えてくるのではないか、と。 世の中には、派手で耳目を集めるようなビジネスが多いかもしれない。一方で、マンション管理のように縁の下の力持ちとして日々の暮らしを支える仕事がある。それは決して地味なだけではない。住民から「管理会社に任せきりではなく、私たち自身が動いてよかった」と言われた時、あるいは廊下の電気がLEDに変わり、年配の住民が「これで夜でも安心して歩ける」とほっと笑顔を見せた時そこには、確かな誇りと手触りが存在する。そして何より、そうやって築かれた合意や工夫の積み重ねが、“暮らし”というかけがえのない舞台を支えているのだ。 「僕はまだまだこの仕事を続けますよ」と峰平は笑う。一度携わったマンションの住民たちとは、案件が終わってもゆるい繋がりが残り続けることがある。それがまた新たな依頼や相談につながる。インターホンの交換ひとつから始まったやり取りが、いつしか理事会の抜本的改革にまで及ぶこともある。そうして少しずつ管理組合の“力”が育っていくのを見守るのは、何よりも大きな喜びだと語る。 地道な作業だが、そこには確実な充実感がある。ミルドレッド・C・フリックが掲げた「本物のリーダーシップとは、分け合い、引き出すこと」に象徴されるように、管理会社やコンサルタントが一方的に押しつけるのではなく、住民の力を引き出すことが真のゴールだ。だからこそ、峰平は決して諦めず、住民を励まし、必要な知識を惜しみなく提供していく。そのスタンスが「暮らしの専門家」としての存在感を際立たせている。