竹山団地の“砦”
“You matter because you are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.”((Dame Cicely Saunders: A Palliative Care Pioneerより) 「あなたがあなたであるということに価値がある。そしてそれは、人生のすべての日々において変わらない。私たちはあなたが平穏に最期を迎えられることを手伝うだけでなく、あなたが最期の日を迎えるまで生きられるようにできることは全て行います。」 英国近代ホスピスの母、シシリー・ソンダースはそう語った。病気や年齢によってその人の価値が損なわれるわけではなく、最後までその人らしさを尊重するケアこそが医療の根幹である…この考えは、まさに竹山病院の実践理念そのものだ。横浜市緑区の団地の一角に佇む竹山病院。全床が地域包括ケア病棟となっており、神奈川県で初の地域包括ケア病院として現在も運営されている。そこには、半世紀前に巻き起こった小さな革命の気配が、未だに色濃く染みついているようにも感じる。 日本の高度経済成長期、人口集中が進む都市近郊にベッドタウンとして、団地のみならず地域の医療を担うため、救急医療、診療所、歯科、産科が配置された。その一角を担ったのが、大矢病院長の父親、故・大矢 清病院長である。昔はまだ救急車がGPSなど持たない時代。地図を見ながら右往左往する救急隊が、少しでも早く到着できるようにと、個人名ではなく“竹山”の地名をそのまま冠して「竹山病院」と名づけた。実にシンプルで直接的だが、それは「地元の⼈が困ったとき、⼀分でも一秒でも早く医療を提供したい」という激情にも似た強い思いの証だったのだ。 そして時代は流れ、父が他界。バトンを受け取ったのが、現在の病院長である大矢 美佐先生だ。大学病院で循環器内科医としての研鑽を積み、更に都内で地域医療に身を置いていた彼女は、父の死を契機に病院へ戻ってきた。「父が遺した病院を、永続的にこの地に残したい」と決意を固めたとき、彼女の情熱に火がついた。
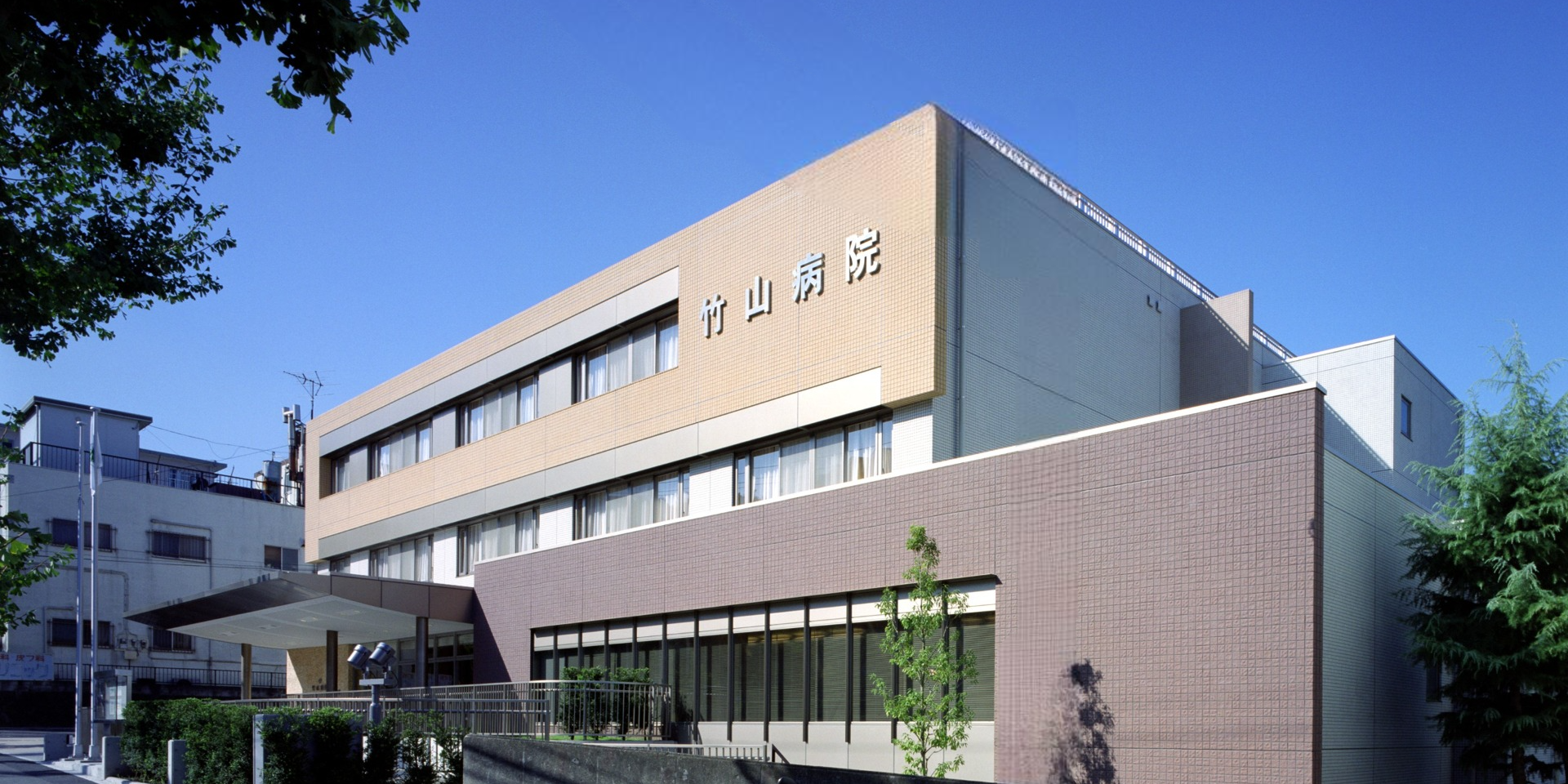
大矢式「時代の読み方」

団地はこの50年で大きく変貌した。かつては家族を築き新居を得た若い世代が1万人を超え、マンモス団地と呼ばれ栄えた。小学校や商店街、歯科、産婦人科などが揃う小さな“街”のようににぎわっていた。しかし年月の経過とともに住民は高齢化し、廃業したクリニックも多い。階段を降りるのがつらいご高齢の方が、処方箋を持って薬局に行くことすら厳しくなった。そこへ目をつけたのが大矢だ。「ならば薬局のほうから上がってきてもらおう」薬局を団地の上部へ呼び寄せ、“足が悪くても薬が受け取れる環境”を整えた。 この「不便ならば形を変えてしまえばいい」という発想は、竹山病院の取り組み全体を象徴している。単に医療を提供するだけではなく、地域の人々の暮らしを支える仕組みを作り、さらには高齢者のデジタル推進サポートをするため、神奈川大学 サッカー部の学生たちを巻き込み「スマホ教室」を開設した。若者と高齢者が出会い、教える・教わるという関係を超えて、まるで昔ながらの子供会と老人会のような温かな交流が令和に生まれたのだ。その取り組みは、コロナ禍が襲った際にも生きた。ワクチン接種の予約がオンライン化され、高齢者のデジタル活用が必要とされたとき、竹山団地では既にその素地ができていたのである。
職員の財布の中身は
白黒テレビは有機ELになり、ラジカセはなくなった。半世紀という歳月は、人々の暮らしを大きく変える。それは地域医療の形も同じで、当時は多くの医師が専門に分かれることもなく、とにかく「なんでも診る」のが当たり前だったとか。竹山病院も例に漏れず、外科・内科の違いを問わず、地域住民が運ばれ来れば即座に対応していた。やがて日本の医療制度が進化し、急性期や回復期、慢性期の役割分担が進んでいく中で、竹山病院は変化を余儀なくされた。しかし、それでも変わらなかったものがある。「家族のような身近な存在として地域のかかりつけ病院になる」という理念と、先代病院長が何よりも大切にした「ここで働く職員を幸せにする」という視点だ。 患者第一主義は病院として当然。だが、それを支える人々の幸せを見落としては真の医療は機能しない。医師や看護師、職員たちが疲弊していては、患者さんに優しく丁寧なケアを提供するどころではないのだ。先代病院長はそこに着目し「職員の財布をパンパンにすることもまた、何より大切だ」と公言していたという。もちろんそれは金銭だけの話ではないが、「生活の不安があっては、良質な医療はできない」という至極現実的な主張でもあった。患者に限らず職員を家族のように思い、まずは実利を保証しながら誇りとやりがいを持ってもらい、ひいては患者を守る…そんな考えが、今も竹山病院に脈々と受け継がれている。

街は変えられる
地域医療は、どんなに改革が叫ばれても病院や自治体だけでは限界がある。だからこそ、大矢は「自分たちだけで抱え込まない」アプローチを好む。自治会や社協、民間企業や大学と連携し、“それぞれの垣根を飲み込んでしまう”ようなイメージで動いているのだ。更に有志住民と“未来先取り倶楽部”を創設し、その活動を広げた。竹山病院は、もはや単なる医療機関ではなく、「住民が安心して生ききるために必要なすべてをバックアップする場所」になりつつある。そして、そうした新しい地域包括ケアの形が、横浜市や各方面からも注目を集めている。 語り口は柔らかいが、その裏に燃え上がるエネルギーは果てしなく凄まじい。「地域包括ケアシステムは必ずしも限られた地域で完結しなければならないという枠組みにしてはいけない。必要ならばさらに外へ広げていくことも必要」 という攻めの姿勢。昔は父が民生委員第一号として地域の隅々を知り尽くしたように、現代の大矢はデジタルや若者とのコラボでエリアを拡張していく。すでに新駅の開通に合わせ、 隣接区への医療連携を強められないかと思案しているという。その言葉には、ひとかけらの疑いや迷いもない。ただ、やるしかないですよね、と笑う。その根底にあるのは「最期までこの地域に暮らしてほしい。そして暮らせるようにする。」という⼀貫した使命感だ。 竹山病院は高齢者救急と回復期のケアを主体に、患者が自宅に戻れるようリハビリや生活支援を徹底して行う。もし自宅へ戻れないなら、特別養護老人ホームや老健施設への案内や連携で、住み慣れた地域での生活を保つ手立てを講じる。医療と福祉を垣根なく組み合わせながら、「もう⼀歩、自分の足で立ちたい」と願う人たちの背中を押すのだ。そこには強烈な使命感と、まさにシシリー・ソンダースが説いた“生きることへの包括的なまなざし”が確かに宿っている。 「自分たちの街を良くするのは、行政だけでも学校だけでもない。自分たち自身かもしれない」。この言葉は、大学生を巻き込んだスマホ教室でも証明された。若者は高齢者にスマホを教え、 高齢者は人生経験から来る豊富な知恵を若者に伝える。いつの間にか“教える側”と“教わる側”が入れ替わる。それは古い時代の子供会や老人会が果たしていた役割のアップデート版とも言えよう。大矢はそこで芽生えた人のつながりが、やがて竹山団地を第二、第三の全世代コミュニティに変えていくと期待している。
最前線を突き進め
かつての日本では、藩医や寺院医が各地で診療所を構え、住民の健康を守る温かな現場があった。江戸時代から、地域に根ざした医療は人々との対話の中で発展し、明治以降の西洋医学の導入と共に技術革新を遂げながらも、伝統的な医療の温かさはその根幹に息づいた。そして今日の日本は、急速な高齢化と都市部への人口集中という複雑な問題に直面している。かつての診療所が象徴する温かいコミュニティ医療は、医師不足や地域間の格差によりその在り方が問われる中、ICT技術の発展により遠隔医療やオンライン診療といった新たな医療形態が生まれている。これにより、伝統的な対面医療の良さと、先端技術による効率化が求められる今、各自治体や医療機関は、地域の特性を活かした持続可能な医療提供体制の確立に向け、日々挑戦を続けている。 地域医療はもはや“お医者さんごっこ”ではない。予防や福祉、教育やデジタルまでもが絡み合い、大きな渦となって街を巻き込んでいく。そして、その渦の中心に立つのが竹山病院であり、大矢美佐なのだ。父の遺志を継ぎつつ、新たな風を吹かせるこの女性院長の姿勢は、シシリー・ソンダースの名言が示す「人生最後の日まで、その人としての尊厳を保証する」ことを、ローカルコミュニティという最前線で実現しようとしているようにも映る。 彼女は、未来を見据えている。コロナ禍であっても、もしくはその先に来る少子高齢化の荒波を前にしても、「この団地と病院が一つになれば、まだまだやれることがある」と信じて疑わない。大きな理想や完璧な準備は要らない。スマホ教室しかり、団地の商店街との連携しかり。最初は目の前のひとつの段差を埋めるだけでいい。でもそのひとつの行動が、やがてはまわりまわって地域全体を動かすエンジンになる。竹山病院はその証左だと言っていい。 地域医療の歴史を振り返れば、そこには常に“人”がいた。誰かの熱意、誰かの助け、誰かの笑顔。それらが重なり合って、この地域を治療する“器”を作り上げてきた。そして今、大矢の手に受け継がれたその器は、新しい時代のかたちへと変貌しながら、なおも拡大を続けている。ソンダースが生涯かけて訴えた「その人の存在自体が尊い」という言葉を、自分の生まれ育った土地で体現しようとする大矢先生。その歩みは、竹山団地を中心に今も力強く続いている。人と街が互いに補い合い、最後まで人生を全うするための医療をどう創り上げていくのか。竹山病院の軌跡は、間違いなく地域医療の可能性を示すひとつの輝くモデルとなるだろう。



