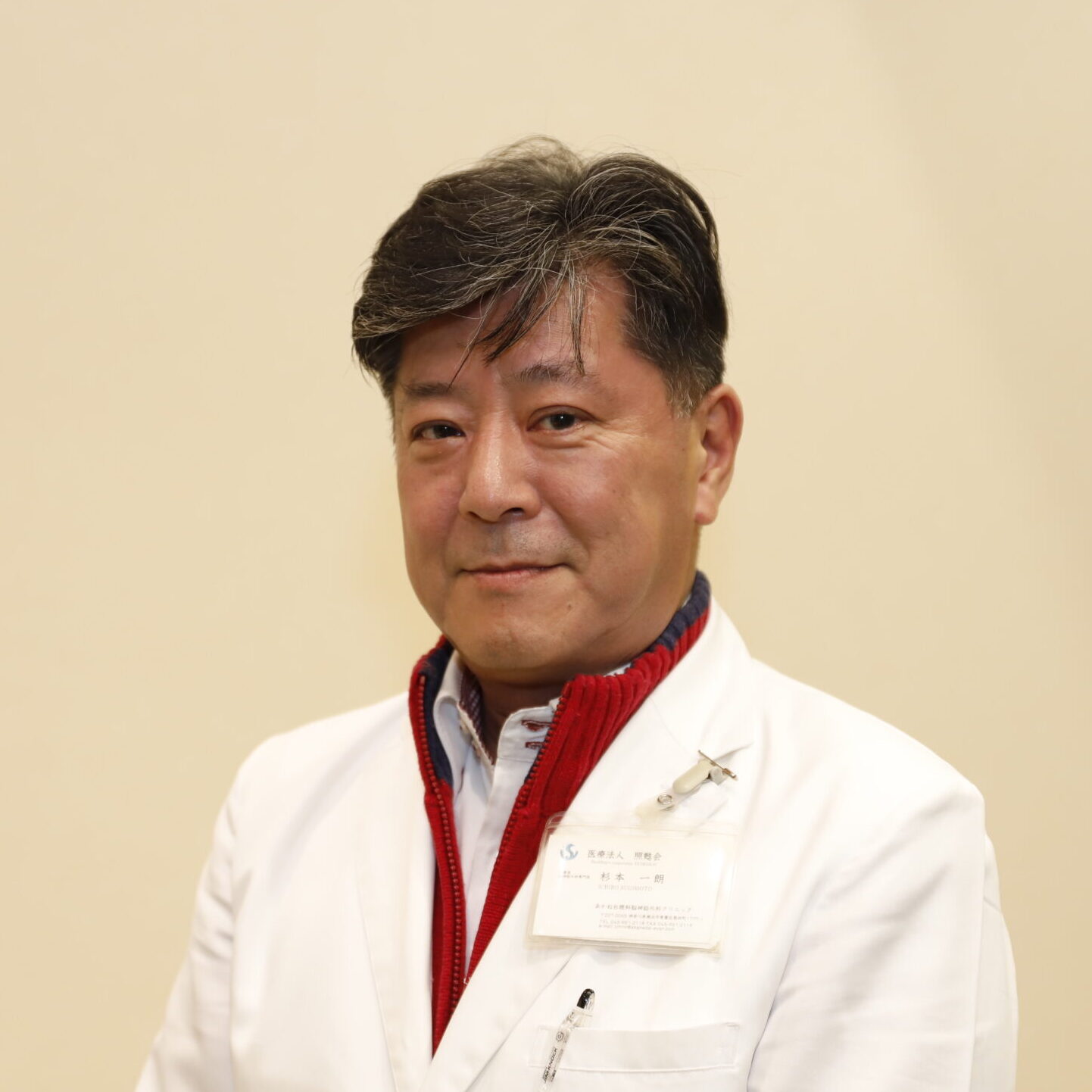青葉区民の灯台的存在
横浜市青葉区。この地域は、豊かな緑と穏やかな街並みが広がり、都市と自然が調和した住環境を提供している。都心へのアクセスも良好でありながら、落ち着いた雰囲気が住民に愛されている。この地に、長きにわたり人々の健康を見守り続ける一人の医師がいる。 杉本一朗。彼が理事長を務める「あかね台眼科脳神経外科クリニック」は、単なる医療機関ではなく、人々が自らの健康を見つめ直すための灯台のような存在である。 幼き日の杉本は、父親の胃がんによる急逝という、誰もが背を向けた絶望と無力感に深く打たれた。あの苦い記憶が、彼の心に火をつけ、医学の道へと導いたのである。父の最期を前に、冷たく淡々と告げられた「運命」という言葉。その響きは、決して甘くはなかった。だが、彼は決意した…人の命を救うという、あまりにも重く尊い使命に身を投じると。

医療観の瓦解、そして再構築

医学の道へ進むことを決意し、東海大学医学部を卒業後、やがて脳神経外科という過酷な領域へと足を踏み入れた杉本。しかし、彼が見たのは、医療の名の下に繰り広げられる厳しい現実だった。当初は外科医を目指していたと語る杉本。「医者になれば、父のような患者を救えるかもしれない。」そんな希望を抱いて医学の道を歩み始めていた。しかし、大学の臨床実習で目の当たりにしたのは、想像とはかけ離れた医療現場の実態だった。緊迫した手術室の中で交わされる言葉は、まるで患者が単なる「症例」や「作業対象」であるかのようだった。治療すべき「人間」ではなく、処理すべき「ケース」として語られる患者たち。術式の成否を競うような言葉、経過を予想する声、そして時にはその命の行方すら軽んじるかのような会話…。 「なぜ、命を扱う医療の現場で、こんなにも無機質なやりとりが交わされるのか?」と、強い違和感を覚えた。しかし、今になって思えば、あの時の医師たちもまた、この過酷なシステムの中で、生き残るためにそうせざるを得なかったのかもしれないと、杉本は振り返る。限られた時間の中で多くの患者を診なければならず、常に膨大な責任を背負い、心をすり減らしながら働き続けていた。彼らにとって、感情を押し殺し、医療を効率的にこなすことは、もはや生き抜くための術だったのかもしれない、と。しかし当時の自分には、それがどうしても受け入れがたかった。 医師とは、患者の命と向き合い、その人生を救う存在のはずだった。しかし、目の前の現実は、自分が信じてきた「医療」とはあまりにも異なっていた。理想と現実の間で大きく揺さぶられた杉本は、問いかけずにはいられなかった――「医療とは、一体何なのか?」と。幾重にも折り重なる運命の中、スーパーローテーションで脳神経外科を経験したとき、彼の医療観はまた大きく変わった。そこには、患者に真正面から向き合う医師がいた。その医師こそ、患者の命を本当に預かる者であり、まさに己の信念に基づいて戦う戦士であった。その誠実な姿勢に雷に打たれたかのような衝撃を受けた杉本は、そこで脳神経外科の道を選ぶ決意を固めた。生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた患者を救うため、寝る間も惜しんで働く日々が続いた。脳卒中の患者が後遺症に苦しむ姿を目の当たりにする中で、彼は思った。「そもそも病気にならなければいいのではないか?」と。病気を治すことだけが医療ではない…杉本の信念は、次第に予防医療へと向かうようになった。 しかし、病院勤務ではこの考えを実現するのは難しかった。しかし、当時の病院のシステムの中では、この考えを実現するのは難しかった。病気の治療に重点を置く医療システムでは、予防医療に力を注ぐことが経済的にも許されなかった。つまり病に倒れた時にのみ手を差し伸べる、いわば『後追いの医』であったのである。 そこで、杉本は決断する。「結局、自分でやるしかない。そう思いました。」杉本は2003年、青葉区の静謐な町並みに、あかね台眼科脳神経外科クリニックを開業。そこでは、病気を治療するだけでなく、患者が健康を維持できるように導くことを理念とした。都市の喧騒から一歩引いた場所にありながら、豊かな自然と穏やかな人情に満ちた、まさに「いやし」を体現したクリニックだ。 そんな杉本が追求する新しい医療の形は、ときに「従来の医療の枠を外れすぎている」と批判に晒されることもあった。しかし、それは彼にとって新たな挑戦の合図でもあった。批判を受けるということは、すなわち新しい価値観を提案している証左である。彼は時代の風向きを読み、既存の枠組みに安住することなく、あえて困難な道を選び続けた。「病気の根本原因を探り、日々の生活習慣や環境を改善することによって、病気そのものを未然に防ぐ。これこそ、未来の医療だと思っています。」
ここは健康「構築」クリニック
あかね台眼科脳神経外科クリニックは、単なる医療機関ではない。ここでは、最新の1.5テスラオープンボアMRIを活用し、患者の負担を最小限に抑えながら高精度な診断を行っている。また、環境と健康のつながりを重視し、腸内フローラや微生物環境の改善を医療の一環として取り入れるなど、従来の枠を超えたアプローチを実践している。診療だけにとどまらず、栄養学や生活環境の改善指導を通じて、患者が自らの健康を管理できるよう導くことが特徴だ。 つまりここでは、薬を使うことよりも、生活習慣を見直し、自己治癒力を高めることが重要視される。杉本は、医学とは本来、人間の生命力を最大限に引き出すためのものであると信じているのだ。 さらに、地域の健康支援として、微生物資材を活用した自然栽培プロジェクトを展開し、収穫された野菜を子ども食堂へ提供するなど、医療と地域貢献を融合させた取り組みも行っている。ここは、病気を診る場所ではなく、健康を創る場所なのだ。

診るのは病気ではなく人生
ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』に登場するウリッセは戦争を終え、故郷へ戻るために苦難の旅を続けた。幾度も嵐に巻き込まれ、神々に試され、それでも決して諦めずに進み続けた。誘惑や恐怖、絶望に打ち勝ちながらも、彼は常に故郷を目指し、知恵と勇気で試練を乗り越えた。 杉本の人生もまた、常識の壁に挑み続ける旅のようである。医療の世界において、確立された価値観に逆らい、新たな道を切り開くことは決して容易ではない。時に批判を浴び、孤独を感じることもある。しかし、それでも彼は諦めなかった。どんなに困難が待ち受けていようとも、患者の健康を守るため、自らの信念を貫き続けてきた。どんなに困難が待ち受けていようとも、患者の健康と向き合うため、自らの信念を貫き続けてきた。 「どんなときでも、最後は自分の可能性を信じるしかありません。時には壁にぶつかり、社会の常識に押しつぶされそうになることももちろんあると思います。しかし、そんな時でも自分自身の信念を大切にし、目の前の課題に挑戦し続けることで、自分自身は納得できる人生を歩めると思うんです。」 従来の医療の枠組みに疑問を抱きながらも、新しい道を切り開いてきた杉本。その過程で多くの批判を受けながらも、信じた道を貫き、患者と向き合い続けている。成功への道は平坦ではないが、挑戦し続けることでしか見えない景色がある。だからこそ、若者たちにも、与えられた枠に収まるのではなく、自らの信念を貫いてほしいと願っている。 杉本一朗という医師は、単に病を診るのではない。彼の目の前には、一人ひとりの人生がある。そして、その旅路を照らす光になろうとしている。